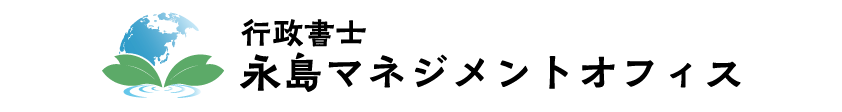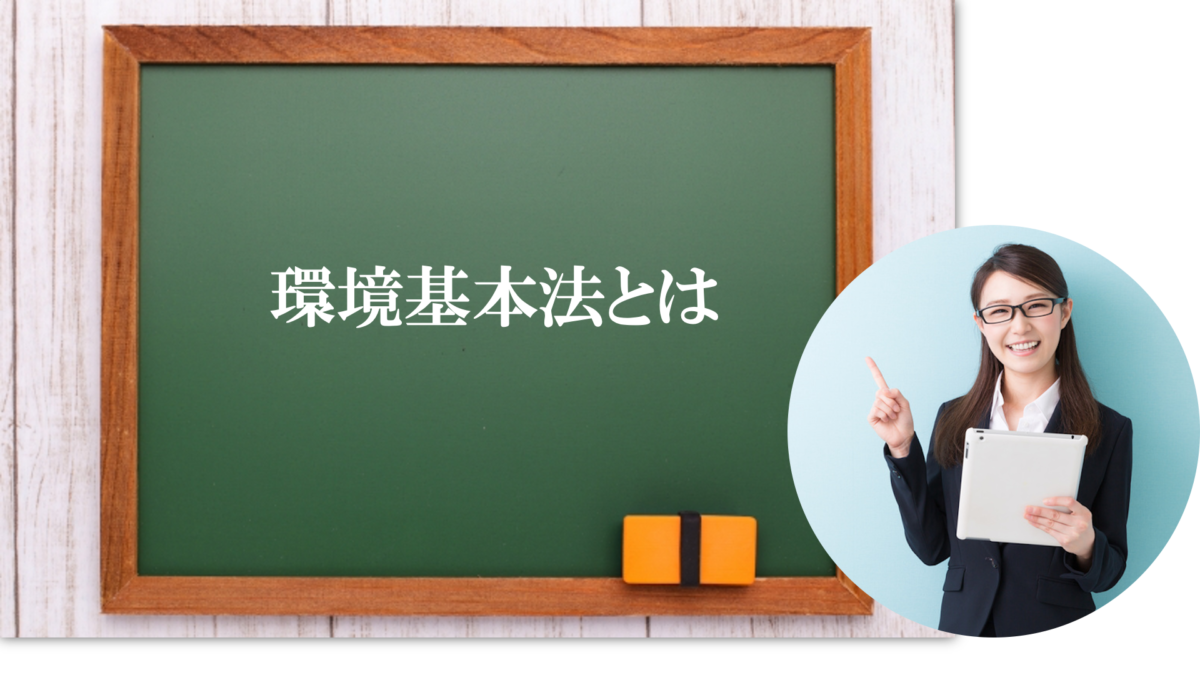基本法の性格
環境基本法とは、その名との通り、
環境保全に関する種々の施策を総合的かつ計画的に推進する法的枠組みを定めた法律になります。
平成5年に公害対策基本法に代わって、地球環境保全などの新たな社会的要請を踏まえて制定されました。
前提として、「基本法」の性格として、
「国の政策の基本的な方向を示す」
ことが主な内容となっています。
対象が、「国」なので大きな枠組みと捉えることが特徴です。
いわゆる「プログラム規定」とも呼ばれています。
一方、基本法と対比して一般の法律を「個別法」と呼ぶことがあります。
「個別法」とは規制措置を定めたり、税制を定めたりというように、
国民や事業者の権利義務に関わる事項を具体的に規定していることが特徴です。
違反した場合の、罰則規定もあるので注意が必要です。
| 名称 | 対象 | 内容 |
| 基本法 | 国 | 国の基本的な方向性を示す |
| 個別法 | 国民や事業者 | 国民や事業者の権利義務に関わる事項を具体的に規定。罰則規定あり。 |
環境保全の基本理念及び指針
本法では、環境保全の基本理念を次のように示しています。
また、国などの施策策定の指針としては、次のように定めています。
事業者の責務
本法8条には、「事業者の責務」として、次の4つを示しています。

本法は、環境保全の基本理念などと共に、国などの基本的な施策を提示しています。事業者の責務規定があり、参考にすべきですが、具体的な義務を定めたものではありません。
よって、本法を環境マネジメントシステム(EMS)に反映させるかどうかは、
組織の判断になります。
一方、組織がEMSを構築・運用する際に、本法の理念や事業者の責務について活動の指針として活用することはできるでしょう。