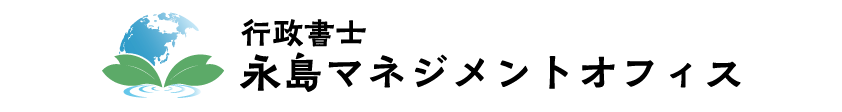省エネ法「エネルギー使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」は、
日本の地球温暖化対策の中で、企業を規制するという意味では中心となる法律です。
日本のエネルギー対策の1つの柱である省エネルギー政策は、最も重点をおく分野であることから、
非常に改正が多い法律となっております。
この法律の適用を受ける事業場等
①特定事業者:年間のエネルギー使用量(原油換算)が1,500kl以上の事業者(連鎖か事業者を除く)。
②特定連鎖化事業者(フランチャイズチェーン):年間のエネルギー使用量が、1,500kl以上である連鎖化事業者。
③特定貨物輸送事業者:自動車200台、鉄道300両、海運2万総トン以上の保有事業者。
④特定旅客輸送事業者:鉄道300両、バス200台、タクシー350台、海運2万総トン以上の保有事業者。
⑤荷主:
・自らの事業に関して貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者(1号荷主)
・自らの事業に関して他の事業者との契約その他の取決めにより当該貨物の輸送方法、日時、場所等を実質的に決定している者(2号荷主)
⑥特定荷主:前年度の輸送量が3,000万トンキロ以上である荷主。
その他、全ての事業者に、エネルギー使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に努めるとともに、
電気の需要の最適化に資する措置を講ずるように努めることを求めています。
適用を受ける事業場等はしなければならないこと
①エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者の選任義務。
※製造業等5業種に該当する工場等で、単体で3,000kl以上となる場合は、別途エネルギー管理者の選任義務。
他、単体で1,500kl以上の場合等は、エネルギー管理員の選任義務。
②中長期計画の提出義務。
③エネルギー使用状況等の定期報告義務。
①中長期計画の提出義務。
②エネルギー使用状況等の定期報告義務。
①中長期計画の提出義務。
②委託輸送に係るエネルギー使用状況等の定期報告義務。
トップランナー制度とは
機械器具等(自動車、家電製品や建材等)に係る措置として、『トップランナー制度』による省エネ基準を導入しています。
トップランナー制度は、性能向上における事業者の判断基準を、現在商品化されていて、かつその中でエネルギー消費効率が最も優れているもの(トップランナー)の性能、技術開発の将来の見通し等を勘案して定め、機器等のエネルギー消費効率のさらなる改善推進を行なうものです。
トップランナー制度では、対象となる機器や建材の製造事業者や輸入事業者に対し、エネルギー消費効率の目標を示して達成を促すとともに、
エネルギー消費効率の表示を求めています。
現在、トップランナー制度対象機器は、自動車・エアコン・冷蔵庫等の32種類が定められています。
令和5年施行の改正とは
令和4年、改正省エネ法が成立し、5年4月に施行されました。
最大のポイントは、2050年のカーポンニュートラルの実現を目指し、図表の通り、事業者へ省エネだけでなく、非化石エネルギーヘの転換を求めたことです。
非化石エネルギーとは、石池や天然ガス、石炭などの化石エネルギー以外のものです。
太陽光発電などの非化石電気、太陽熱などの非化石熱、水素、アンモニアなどがあります。
改正後は、取り組むべき省エネの、非化石エネル対象範囲を拡大しギーの省エネにも取り組みます。
また、特定事業者等には、非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期計画の提出とともに、
非化石エネルギーの使用状況等の定期報告書の提出が義務付けられました。
国が定めた判断基準に沿って、使用した電気全体に占める非化石電気の比率に関する目標を設定し、計画の策定や実績報告が求められます。
このうち、鉄鋼業(高炉・電炉)、セメント製造業、製紙業(洋紙・板紙)、石袖化学業(石池化学系基礎製品製造業・ソーダ工業)、自動車製造業の五業種・八分野については目安が設定され、目安に対する目標設定や計画の報告義務があります。
建物への省エネ基準適合義務
令和4年6月、建築物省エネ法「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」
が改正され、7年4月より省エネ基準適合義務が大幅に拡大されます。
原則として、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合が義務付けられます。
例えば、小規模な非住宅や住宅にも規制対象となります。
最後に
エネルギー使用量1,500kl以上/年などに該当し、特定事業者に認定されると、
毎年、中長期計画の提出義務やエネルギー使用状況等の定期報告義務が伴います。
通常業務の中で、これらの書類を作成し提出するとなると結構な時間と手間がかかります。
当事務所は、環境関連法の遵守義務に基づく、各種「届出・報告」の作成、提出までも承っておりますので、お気軽にご相談ください。