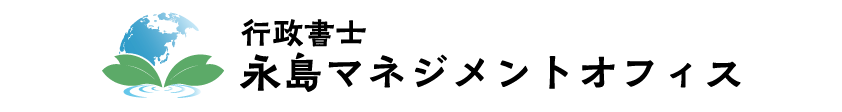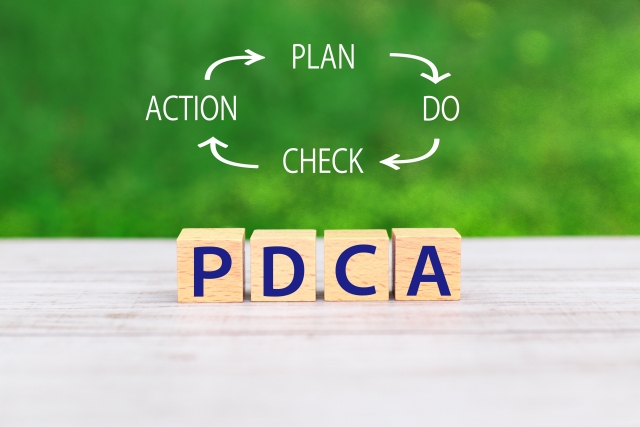PDCAとは
ISO14001やエコアクション21などを活用し、
環境マネジメントシステム(EMS)を構築・運用する中で、
「PDCAサイクル」により、環境法対応の仕組みも整備している企業は多くあります。
PDCAの基本的な仕組みは次の通りです。
計画を作る。
計画通り実施する。
計画通り実施したかチェックする。
計画通り実施し、チェックするプロセスや結果を踏まえて、次のステージに向けて見直す。
PDCAモデルに環境法対応を落とし込むと、まず
「P」では、自社に適用される環境法の規制がどのようなものなのかを把握することになります。
多くの企業では、「法規制登録簿」などと呼ぶ、適用規制をまとめた一覧表を作成していることでしょう。
次に「D」では、それに基づき、環境法対応を行い、
「C」では、順守評価を行います。
「A」では、環境法の対応状況全般について適切・有効であったかを判断します。
形骸化するPDCA

「Plan」(計画):分厚い法規制一覧表。
何が義務化よくわからない。
「Do」(実行):廃棄物や化学物質等の取扱い手順書はあっても、利用されない。
「Check」(チェック):順守評価はいつも「○」。
しかし、その根拠は不明。
「Act」(見直し):経営層への報告は毎年
「法違反なし」。しかし、現場は不安でいっぱい。
様々な企業において、環境法に逸脱するトラブルが散見されます。
それは、PDCAサイクルの各段階で活動が形骸化していることが少なくないからです。
例えば、上記のように、
「P」では、法規制の一覧を作成しているものの、あまりに分厚い一覧表であり、利用しづらいものが散見されます。
「D」では、法規制に対応する部門に手順書があっても、現場では実際には利用していないことがあります。
「C」では、順守評価を行なっているものの、評価者が何を根拠に「○」と評価しているのか不明な場合があります。
「A」では、環境法の対応にISO事務局が力量不足などで不安があるにもかかわらず、経営層にそれが伝わっていないことがあります。
PDCAでまわす環境法対応〜改正ISOにヒントあり〜
ISOのPDCA

環境マネジメントシステムの適用範囲
「Plan」(計画)
・順守義務の決定、参照、文書化
・リスク及び機会の決定
「Do」(支援及び運用)
・順守義務を考慮に入れた目標
・順守義務を満たす力量
・順守義務への認識
・外部コミュニケーション
「Check」(パフォーマンス評価)
・順守評価(頻度決定)、処置、
文書化、知識、理解の維持
「Act」(改善)
・順守義務の変化、適合傾向を考慮して、
マネジメントレビューを行う。
ISol4001は2015(平成二七)年に大幅改正されています。
その新たなPDCAサイクルに組み込まれた環境法対応の仕組みを見ると、対応の形骸化克服に向けたヒントがたくさん詰まっています。
上記のように、まず、
「P」では、「順守義務」(環境関連の法律、条例、地域との協定などを指す)にどのようなものがあるかを参照できるように文書化を求めています。また、組織の状況や順守義務を踏まえた「リスク及び機会」を決定することも求めています。
「D」では、順守義務を考慮に入れた目標達成活動を行うとともに、順守義務に関連する力量の確保や外部とのコミュニケーションなどに努めます。
さらに、
「C」では、順守評価を定期的に実施し、問題があれば対応していきます。
「A」では、一連のPDCの実施状況を報告するとともに、順守義務の変化も考慮しながら経営層がレビューします。
そして、問題点があれば、対策などを指示し、次のステージに移行させることになります。
リーダーシップの強化へ
こうしたPDCAに実効性を持たせるために最も大切なものは、
IS014001の2015年版で強調される「リーダーシップ」ではないかと思われます。
環境法に対応することよりも、売上や利益を重視する企業では、こうした環境法対応の仕組みと運用は形骸化しがちです。
しかし、経営層が法令遵守の徹底を明確に打ち出せば、それに従わない社員は少ないはずです。
実は、環境法対応に精力的に取り組む企業の多くには、こうした経営者がいるというのが筆者の実感です。
環境管理責任者やISO事務局の立場であれば、自ら法令違守に動くだけでなく、
経営者に法令遵守の必要性を働きかけ、経営者からその徹底を指示させることが、
PDCAの各段階での実効性を高めることにつながるでしょう。