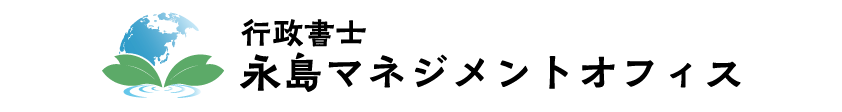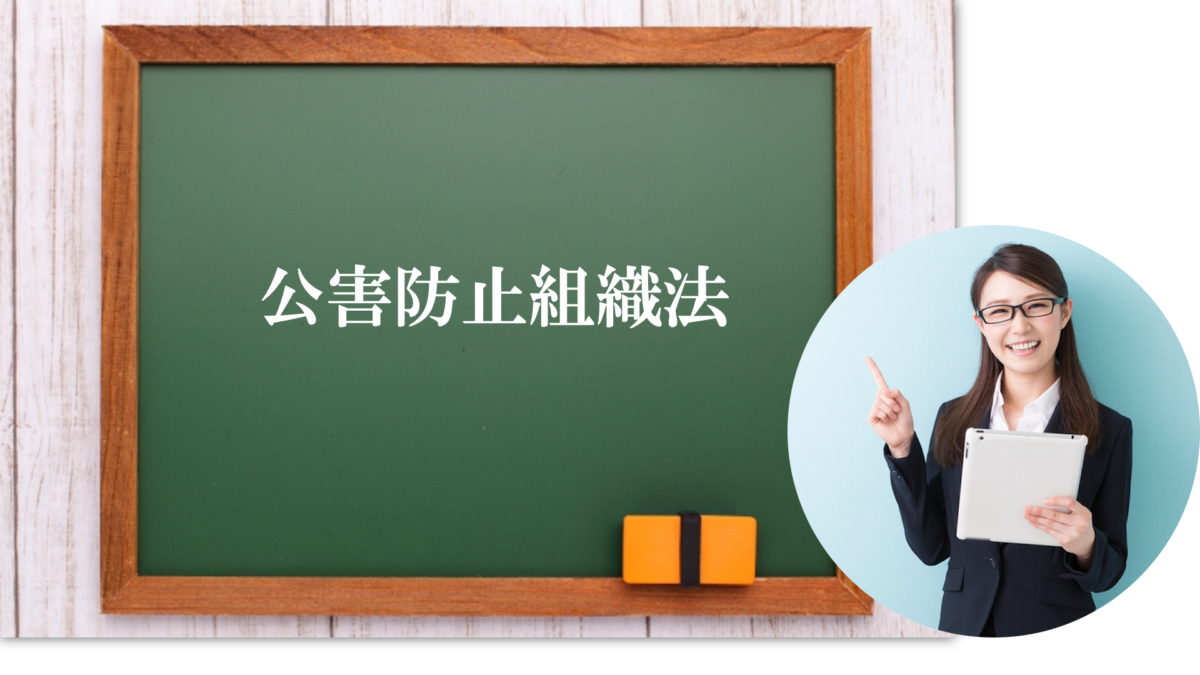この法律の適用を受ける事業者
公害防止組織法は、環境負荷の大きい工場を対象に、大気汚染防止法などに基づく規制を遵守するための体制整備を求めた法律です。
この法律の適用を受けるのは下記に該当する場合になります。
①製造業(物品の加工業も含む)
②電気供給業
③ガス供給業
④熱供給業
この法律では、「悪臭」「地盤沈下」「廃棄物」については、対象としていないのが注目ポイントです。
悪臭については、その発生源が多種多様でその発生施設を特定することが難しい為。
地盤沈下については、工業用水法又は、ビル用水法によって地下水の汲み上げ規制されている為。
廃棄物については、廃棄物処理法が適用される為。
以上の理由から対象外になっています。
①ばい煙発生施設
②特定粉塵発生施設
③一般粉塵発生施設
④汚染等排出施設
⑤騒音発生施設
⑥振動発生施設
⑦ダイオキシン類発生施設
各施設によって対象条件が設定されていますので、詳細は条文を確認しましょう。
例:ばい煙発生施設の場合、
①大気汚染防止法による「ばい煙発生施設」のうち「有害物質」を発生させる施設を設置している工場。
②上記以外の工場全体の「ばい煙発生施設」からの排出ガス量が1万m3 /時以上の工場。
適用を受ける事業者がしなければならないこと
「特定工場」に該当する工場では、
①公害防止統括者
②公害防止主任管理者
③公害防止管理者
を選任し、選任してから30日以内に都道府県知事に届出をしなければなりません。
| 役職 | 役割 | 資格 |
| 公害防止統括者 | 工場の公害防止対策の責任者 | 不要 |
| 公害防止主任管理者 | 公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する | 国家資格必要 |
| 公害防止管理者 | スペシャリストとして公害防止対策の技術的事項を担当する | 国家資格必要 |
都道府県知事は、
・工場等で公害関係法規に違反し、住民に被害を与えたような場合には、これらの公害防止管理者又は、その代理者を
解任するように命令することができます。
・公害防止管理者の職務の実施状況の報告を求め、その工場に立ち入り検査を実施することができます。

資格を持つ社員がいないために公害防止管理者を選任できない、なんてことがないように、計画的に対応していきましょう。