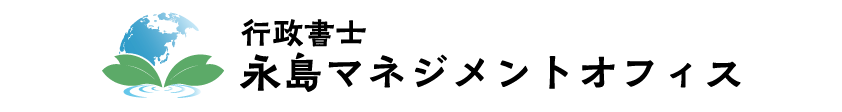環境関連法規だけで、約80種類あります。
その中で、主な環境法規を確認してみましょう。
環境基本法
<地球環境>
・省エネ法
・建築物省エネ法
・温暖化対策推進法
・フロン排出抑制法
・オゾン層保護法
・再エネ特措法
・気候変動適応法
<公害>
・公害防止組織法
・大気汚染防止法
・自動車NOx・PM法
・水質汚染防止法
・浄化槽法
・下水道法
・海洋汚染防止法
・土壌汚染対策法
・騒音規制法
・振動規制法
・悪臭防止法
・工業用水法
・ビル用水法
<廃棄物.3R>
・循環型社会形成推進基本法
・廃棄物処理法
・バーゼル法
・PCB廃棄物特措法
・資源有効利用促進法
・プラスチック資源循環法
・各種リサイクル法
(容器包装リサイクル法)
・グリーン購入法
<化学物質等>
・化審法
・化管法
・毒劇法
・ダイオキシン特措法
・水銀汚染防止法
・労働安全衛生法※
・消防法(危険物)
・高圧ガス保安法※
<生物多様性等>
・自然環境保全法
・自然公園法
・環境影響評価法※
・鳥獣保護管理法
・種の保存法
・カルタヘナ法
・外来生物法
・工場立地法

エコアクション21の対象となっている法律は黄色マーカーになります。
(※は対象とするかは組織の判断によるもの)
事業を行うにあたって必ず遵守しなければいけません。
法律の簡単な捉え方
環境担当の方には、法律に苦手意識がある方も多いかと思います。
以下の3つの要点を押さえれば理解しやすくなると思います。
01
規制対象を探す
環境関連の法律は、地域や設備、物質、規模などで、規制すべき対象を決めています。
まず、自社が規制対象となっているかどうかを確認してみましょう。
02
業務内容を探す
その法律が、規制対象に対してどのような義務を課しているかを確認します。
義務には、届出義務や規制基準の遵守義務などがあります。
03
担保措置を探す
義務を課す条文を定めても、それに違反した場合の制裁がなければ誰もそれを守ろうとはしません。そこで、義務に違反した場合の罰則等の担保措置を定めています。
担保措置として、基準違反であれば、改善勧告や改善命令が出され、それに違反すれば罰則が適用されます。

多くの環境法が以上のような仕組みなっています。
環境法を読むときは、まずはその法律の全体像を眺め、
規制対象を確認し、自社が該当するか否かを確認してみましょう。
「法律・政令・規則」セットで法令を読む
法令の規制事項を把握しようとする時、「法律・政令・規則」を意識しながら、
関連法令を探すのがわかりやすいでしょう。
一つの法令だけで、規制内容が全て定められているケースはほとんどありません。
通常は、複数の法令・政令・規則が一つのかたまりとなって規制体系を形作っているものです。
このことを意識しながらセットで法令を読むと理解しやすくなります。
水質汚濁防止法の例
| 法令の種類 | 位置付け | 関連する法令(例) |
| 法律 | 政令等の上位にあり、国会が定める | ・水質汚濁防止法 |
| 政令 | 施工令などがあり、内閣が定める | ・水質汚濁防止法施行令 |
| 省令等 | 施行規則などがあり、大臣等が定める | ・水質汚濁防止法施行規則 ・排水基準を定める省令 |
| 告示 | 大臣等が定める | ・環境大臣が定める排水基準に係る検定方法 |

法律の下に下位法令等がいくつもあります。
「法令・政令・規則」をセットで読むのがコツです。