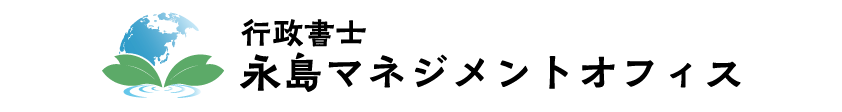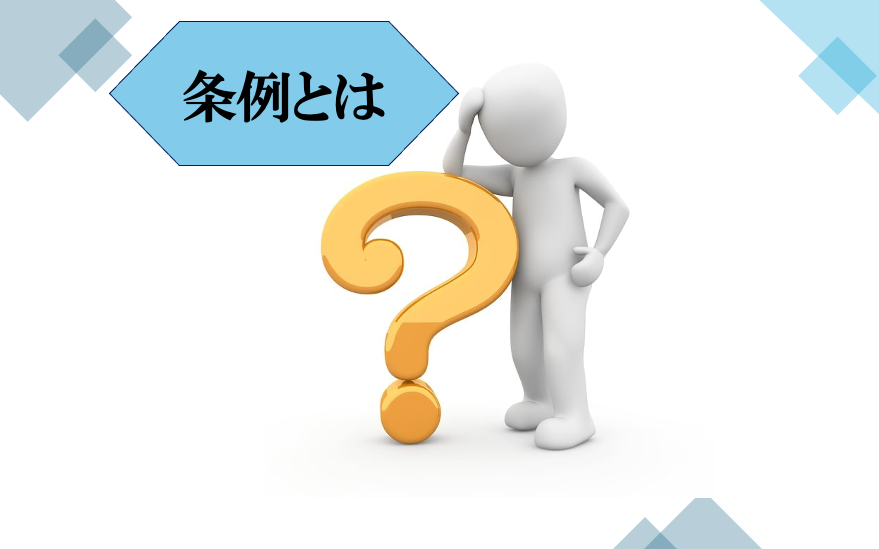気付けば条例違反しているかも?
国の法規則には対応していても、
地方自治体の条例規則にまで対応できている企業はそれほど多くないのかもしれません。
ある企業においては、国の法令を調べる社内手順はあっても、
条例を調べる手順が実質なく、そうした中で、
長年条例違反していることに気付かずに操業してきたという事実もありました。
条例には、国の法規制とは別に独自の規制を設けている条例は多数あります。
公害規制はもちろん、温暖化対策の独自規制もあります。
大規模に温室効果ガスを排出する都道府県内の事業所に対策計画等を義務付ける規制などもあります。
都道府県ばかりではありません。
市町村の条例にも注意が必要です。
例えば、大規模な建築物において廃棄物管理者の選任や減量計画の提出義務を
課している廃棄物条例も珍しくありません。
こうした自治体の条例に対応していない企業が散見され、時には行政指導を受けています。
継続的な対応手順の確立が求められています。

条例もきちんと調べないければいけません。
環境条例の調べ方
条例は、国の法令に違反しない限り、都道府県や市町村の判断で、自由に作ることができます。条例の名称も様々です。
ただ、全国の環境条例を見ていると、一定の傾向を読み取ることはできます。
これを踏まえて条例を調べると、だいぶ楽になるはずです。
すべての都道府県には、「生活環境保全条例」や「公害防止条例」などと呼ばれる条例があります。
国の法令の場合、「大気汚染防止」は大気汚染防止法などで対応するなど、個別の環境テーマごとに一つの法令を作っています。
しかし、地方自治体の場合は、大気汚染を含む公害全般の規制などを―つの条例で定めているのが一般的です。
生活環境保全条例は、かつては公害防止条例でした(現在でも公害防止条例のままの自治体もあります)。
それを、地球温暖化や廃棄物、化学物質などの対策も盛り込み、公害防止条例をいわばバージョンアップさせて、現在の姿になりました。
この条例では、大気・水質・騒音・振動について、ほぼすべての都道府県で、国の法律の対象施設以外の施設に対して届出・規制基準遵守などを義務付けています。
生活環境保全条例とは別に、温暖化対策条例を独立させて制定している自治体もあります。
大規模排出事業者への計画書提出制度などを定めているところもあります。
さらに、廃棄物対策条例を定めている自治体もあります。排出事業者への処理委託先への実地確認義務など、独自規制が多いのが特徴です
環境条例を調べるときの「3×2ステップ」
企業が環境条例を調べる際には、まずは生活環境保全条例を調べる必要があります。
その次に、温暖化と廃棄物の条例をそれぞれ調べます。
自治体は都道府県と市町村の二層構造になっているので、
自社の所在地にある都道府県と市町村それぞれについて、
この3ステップを踏んだ調査を2回行うという、
いわば「3×2」ステップで、最低限の調査を効率よく行うと良いでしょう。
都道府県・市町村 それぞれに下記のステップで調べましょう。
STEP 1
生活環境保全条例を調べる。
・地球温暖化対策の規制があることも
・廃棄物規制があることも
・その他、化学物質、自然環境などの規定があることも
STEP 2
温暖化対策条例を調べる。
・生活環境保全条例とは別に、大規模排出時事業者への計画書提出制度などを規定
STEP 3
廃棄物対策条例を調べる。
・排出事業者への処理委託先への実地確認義務など、独自規制が多い

条例にはある程度パターンがあるから、
それに沿って調べていけばいいんだね。

条例の名称や具体的な内容は、
自治体によって様々なので注意しましょう。